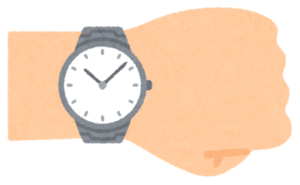DJI Osmo Action 3の熱暴走は本当?原因と対策を徹底解説

「せっかくDJI Osmo Action 3を買ったのに、30分も経たないうちに熱で止まってしまった…」 そんな声を耳にした方も多いのではないでしょうか。アクションカメラは小型かつ高性能である反面、内部にこもる熱との闘いが避けられない宿命を抱えています。特にDJI Osmo Action 3は4K撮影性能に優れているため、映像の美しさを追求するほど発熱しやすいのです。
ユーザーの中には「真夏に海辺で使ったら5分で熱暴走した」「スキー場では全く問題なかった」といった相反する体験談を語る方もいて、環境要因も無視できません。つまり熱暴走の要因はひとつではなく、カメラの設定・周囲の気温・直射日光など複合的な条件によって左右されるのです。
この状況に悩むユーザーは、「熱対策の正解って結局どれ?」「GoProとどちらがマシなんだろう?」と疑問を持ちがちです。そこでこの記事では、DJI Osmo Action 3が熱暴走を起こすメカニズムをわかりやすく解説し、すぐ実践できる発熱抑制テクニックを紹介していきます。アクションの一瞬を逃さないために、正しい知識と対策を身につけておきましょう。

Insta360 X5 通常版 – 防水8K 360度アクションカメラ、高い暗所性能、見えない自撮り棒効果、頑丈で交換可能なレンズ、3時間バッテリー、ウィンドガード内蔵、手ブレ補正、トリプルAIチップデザイン
アクションカメラで熱暴走に強いタイプは、3つぐらいです。上記のInsta360のXシリーズはそれにあたります。Insta360は中華系の企業ですが、その中のガジェット系のジャンルの中でも、かなり熱に対しては強いタイプです。結局熱暴走に対する一番の対策は、他のアクションカメラも使える準備をしておくことじゃないかなと思っています。
DJI Osmo Action3も実は熱には強いタイプで、熱暴走を起こすというような不安をあまり聞いたことがありません。しかし一部そういう声もあるようなので、結局その不安を解消するにはどうしたらいいのか?というところまで書いていこうと思います。DJI Osmo Action3というカメラは一応熱暴走には強いタイプのアクションカメラですが、結局のところ一番簡単なのが複数のアクションカメラを確保しておくというのと、スマホなどもしっかり利用していくというものです。
スマホを使うとこちらならいろいろ対策が立てやすいので、使い分けをしつつDJI Osmo Action3の熱暴走を抑えてください。結局長時間使わないというのが、熱暴走対策になっていくと思うのでこの記事を今読んだ段階で面白いと思ったら、このまま読み進めていただければ幸いです。
【設定編】熱暴走を避ける!DJI Osmo Action 3の「設定」と「冷却」
熱暴走を防ぐためには「カメラ内部の処理負荷を抑える設定」と「外部環境から効率よく熱を逃がす工夫」の二軸で考えることが重要です。どちらか一方だけでは限界があるため、両方を併用することで撮影時間を大幅に延ばすことができます。まずは撮影設定での工夫、その後に物理的な冷却手段を見ていきましょう。
設定に関しては上記の動画の通りにやっていけばいいと思うのですが、冷却手段はちょっと難しいのですがこれもいろいろあります。自分でアクションカメラに張り付けたりできる方なら、以下の方法が有効かなと思います。
- ヒートシンクシール(放熱シール)
- アルミプレート・放熱プレート
- 専用冷却ケージ(フレーム)
しかしこれで解決するとは到底思えないので、もう少し具体的にバイクに対して何をするべきなのか?ということを書いていこうと思います。
長時間撮影もOK!熱停止を防ぐ最適な撮影設定とは
長時間撮影を狙うなら、解像度やフレームレートを現実的な水準に落とすのが有効です。特に4K/120fpsは高負荷すぎるため、安定性を求めるなら4K/60fpsあるいは2.7K/60fps程度に調整するのがおすすめです。この設定なら高精細さを保ちながらも処理負荷を半減でき、夏場の屋外でも動作時間が延びる傾向があります。
また、HDRや高ビットレート記録などの「追加負荷がかかるオプション」を常時使うのは控え、必要なシーンだけ有効化するのも効果的です。たとえばRockSteady(電子式手ブレ補正機能)は便利ですが、常時オンにすると画像処理エンジンがフル稼働します。動きの少ないシーンでは補正をオフにし、必要な場面だけ切り替えることで、発熱を抑えつつバッテリー持ちも改善されます。
4Kは60fpsで十分?画質を保ちつつ発熱を抑える設定
「どうしても4K映像にこだわりたい」というニーズもあるはずです。その場合はフレームレートを抑えることが鍵になります。人間の目で「滑らか」と感じる基準はおおよそ30fps前後と言われています。スポーツやアクションなら60fpsが理想的ですが、120fpsまで必要なシーンは限定的です。臨場感を維持しつつも、熱を最小化するなら4K/60fpsを基準に考えると良いでしょう。
4K/60fpsで撮影を行えばデータ量も半分になり、発熱や消費電力が安定します。その上で必要なシーンだけハイスピード撮影を組み合わせれば、熱暴走を避けながらも表現力を犠牲にせず映像を残すことが可能です。撮影後の編集でスローモーション効果を付ける場合も、この設定でバランスを取るのが現実的な方法といえます。
この設定に関しては下記のような記事を見つけてきました。実はInsta360 Xシリーズは冒頭でも言った通り本当に熱暴走に強いと評判がいいのです。なのでXシリーズの設定をDJI Osmo Action3でもできそうなところまでやってしまえば、熱暴走はともかく設定に関してはあまり問題はないのかなという印象です。

バッテリーやプロモードの使い分けで熱をコントロール
もう一つの重要なポイントがバッテリー運用です。Osmo Action 3のバッテリーは高性能ですが、高出力を必要とする場面では早く発熱します。そのため、撮影予定に応じてバッテリーを複数持ち歩き、短時間で交換するようにすると内部の温度上昇を分散できます。また、充電直後のバッテリーは発熱しやすい傾向があるため、使用前に数分休ませるのも一つのコツです。
さらに、Proモード(マニュアル撮影モード)を駆使してISO感度やシャッタースピードを調整すると、センサーの負荷を抑えられるケースもあります。自動設定では無駄に高い処理を行ってしまうことがありますが、手動設定で最適化すれば発熱を避けつつ、映像表現の幅も広げられるのです。
以前にAnkerのSolix C300というポータブル電源を、フードデリバリー用に使ってみた記事を書いています。バイクから直給電だとバッテリー上がりを起こす可能性もあるので、アクションカメラの電源もポータブル電源から引っ張ってくるやり方もアリです。

【冷却編】DJI Osmo Action3で物理的に熱を逃がす具体的な方法
設定調整だけでは限界があるため、「物理的な冷却対策」も欠かせません。アクションカメラは内部に冷却ファンを搭載していないため、ユーザー自身が工夫して放熱を助ける必要があります。ここからは実際に多くのユーザーが取り入れている効果的な冷却方法を紹介していきます。
外部冷却ファンは本当に効果がある?おすすめの冷却グッズを紹介
まず取り入れやすいのが、外部冷却ファンの使用です。スマートフォン用のクリップ式冷却ファンやペルチェ素子を利用した冷却器具は、アクションカメラにも応用可能です。冷却ファンを背面や側面に装着すれば、空気を循環させて筐体から効率よく熱を逃がせます。特に長時間の定点撮影やライブ配信といった「持ち歩かない使用環境」では、コンパクトな冷却ファンが非常に有効です。
一例として、スマホゲーム愛好者がよく使う「ペルチェ式冷却ファン」は、表面温度を瞬時に下げる性能を持ち、夏場でも効果を実感しやすいアイテムです。ただし、外部電源を必要とするため、フィールドでの機動性を求めるシーンにはやや不向きです。「屋外で短時間撮影」「室内収録で長時間駆動」と目的ごとに使い分けるのが理想的といえるでしょう。
保冷剤をタオルでくるんで冷やすという意見もありましたね。保冷剤を冷やしておくアイテムが必要なので、それはバイクならクーラーボックスが適任でしょう。クーラーボックスはコンテナボックスとも呼びますが、普段は釣りで使うようなアイテムです。しかし私もアクションカメラの冷却に使うとは、ちょっと考えなかったですね。関連記事を書いていたようなので、固定方法などもも気になったら参考にしてください。

ヒートシンクや放熱ケースは必要?効果と注意点を解説
外部アクセサリーの中でも注目されるのが「ヒートシンク」や「金属製放熱ケース」です。ヒートシンクはアルミや銅といった熱伝導率の高い素材を利用しており、カメラ内部から伝わる熱を素早く外気に逃がす役割を果たします。装着するだけで温度上昇を数度抑えられるケースもあり、長時間撮影に取り組むユーザーには人気があります。
ただし、ヒートシンクや放熱ケースには重量増やサイズ拡大といったデメリットも存在します。アクションカメラの「軽量・コンパクト」という本来の強みが損なわれる可能性があるため、使用目的を見極めた上で導入しましょう。また、製品によってはカメラの端子やボタンを覆ってしまうものもあるため、購入前に互換性をしっかり確認することが大切です。
あとこれは私の主観だと思って聞いてもらっていいのですが、バイクをビッグスクーターにするとかある程度積載量の大きなバイクの方が有利じゃないかなと思います。マニュアルバイクとかビッグスクーターとかです。そうすると保冷剤を入れておけるスペースもたくさん作れるので、とても便利じゃないかなとは思います。70万円ぐらいするのでその費用をどう工面するか、というのもネックになりますが。
とはいえ手が全く出ない費用でもないので、もし私の考えが気になるという方は実際に私が気になっているビッグスクーターの記事を載せておきます。あくまでこういう考えもあるのだという一つの参考程度に読んでみてください。

DJI Osmo Action3を熱暴走から守りつつ最高音質で動画を撮影する方法とは?
冷却ファンなどを使用するのも非常にいいやり方です。しかし熱暴走に気を取られていると、一つ問題が出てきます。そのファンの音すらDJI Osmo Action3が拾ってしまうということです。あなたは動画を撮影する目的って、こういうものではないでしょうか?
- バイクのサウンドを最高音質で拾いたい
- 風切り音などの音は入れたくない
- 会話の音など必要な音だけ拾ってほしい
これがバイク撮影で最もネックになるものです。DJI Osmo Action3も素晴らしい性能を持ったアクションカメラなのですが、万能戦士ではないので音質に関してはたくさんの音を拾ってしまいます。逆に言えば3万円台でありつつ出来は最高レベルといういい証明になるのですが。
今回は自分の声を録音するということにだけ特化した話をしますが、風切り音を防ぎつつ音割れも防ぎ録音するには上記の動画で解説されていたZOOMのアイテムでもいいです。

ZOOM ズーム F2-BT/Bフィールドレコーダー ブラック 黒 超小型軽量ウェアラブル 32グラム32bitフロートBluetooth®内蔵モデル 録音・インタビュー・映画・ドラマ・ニュース・Vlog・YouTubeなどのロケーション収録に最適
しかしこのサイトでもさんざん紹介しているCardoなら最高音質で動画の撮影に自分の声も一緒に録音することができます。外部マイクを接続する必要はあるものの、インカムとしても普通に通話もできるし、さらにFMも使うことが可能です。
この場合はちょっとお高めのCardoのモデルの方が使い勝手がいいように感じますが、もし予算に余裕があって音質はいいものがいい、風切り音も防ぎつついい音でDJI Osmo Action3の動画を撮影したいという方がいたら参考にしてください。

ユーザーの疑問を解決!Osmo Action 3の熱対策Q&A
熱暴走問題は多くのユーザーが直面するため、ネット上にも「GoProと比べて熱に強いの?」「熱停止すると故障するのでは?」といった疑問が多数見られます。ここでは特に多い質問に答える形で、事実ベースで整理していきましょう。
それとこういう疑問に対して実際に使っているレビュー動画などは必須だと思いました。なので上記の動画も参考にしてもらって、DJI Osmo Action3を本当に使い続けた方がいいのか?はたまた別のアクションカメラも用意しておくべきなのか?ということも検討材料にしていただければ幸いです。
Q1. GoProと比べてDJI Osmo Action 3は熱に強いの?
結論から言えば、Osmo Action 3はGoPro HEROシリーズと比較しても熱の問題は同等か、やや優位な場面があるといえます。理由は筐体設計にあります。Osmo Action 3は金属フレームを活かした放熱構造を採用しており、外装全体がヒートシンクの役割を果たします。一方でGoProは高い処理性能と小型化を追求した結果、短時間で内部温度が上がりやすくなる傾向があります。
実際のユーザーテストでは、室内で4K/60fps撮影を行った場合、GoProは約25〜30分で停止するケースが多いのに対し、Osmo Action 3は同条件で30〜40分持ったという報告もあります。ただし、真夏の屋外では両機種とも20分前後で停止するなど「どちらも熱の壁は超えられない」という現実は変わりません。したがって、「GoProより熱に強い」=「熱暴走しない」という意味ではなく、むしろ環境次第でどちらも似た状況になると理解しておく必要があります。
詳しい設定がわからない方はこちらの記事も役立つかなと思いました。Insta360の話ではあるのですが、正直に言うとアクションカメラの設定はある程度同じです。熱暴走以外でもアクションカメラで問題は結構起きているようなので、そういった熱暴走以外のトラブルでも役立つ可能性もあります。そのぐらいの軽い気持ちで読んでいただければ幸いです。

Q2. 熱暴走するとOsmo Action 3が故障するリスクはある?
多くのユーザーが不安に思うのが、「熱による停止=故障」ではないか、という点です。ここで押さえておきたいのは、Osmo Action 3には自動保護機能が備わっているということです。一定温度に達するとセンサーや基盤のダメージを避けるため、自動的に録画を停止し電源を落とします。これは本体を守る設計であり、停止したからといって即故障に直結するわけではありません。
ただし注意すべきは、「繰り返し高温状態で使用し続けると徐々に劣化が進行する」という点です。特に影響を受けるのはバッテリーで、高温下では膨張や持続時間低下のリスクが高まります。また、長期間におよぶ過熱使用は基盤や接点の寿命を縮める恐れもあります。そのため、メーカーが推奨する環境条件(通常0℃〜40℃での動作)を守り、一定時間使用したら冷却休憩を取ることが長寿命の秘訣といえるでしょう。
Q3. これ以外の設定でも熱暴走の故障が防げない場合は?
このトラブルの対処法は3つあると思います。
- バイクにコンテナを積む
- 別のアクションカメラも用意しておく
- シートバッグも用意しておく
この3点ぐらいが実はアクションカメラの熱暴走に対する最も有効な対策です。シートバッグはなんでか?って話なのですが、荷物を分散できるので先ほど言ったようなクーラーボックスを冷却専用に使えるという点です。
PCXカスタム!タナックスのシートバッグは長距離ツーリング向き? – ポレポレ日記
PCXでできるなら当然フォルツァ250でもXMAX250でもOKです。私がPCX160をあまりこの記事で信奉していない理由は、DJI Osmo Action3に限らずアクションカメラの熱暴走に関しては、とにかく収納力が必須ということです。アクションカメラを使う状況とはどういう状況でしょうか?
- 300㎞以上のツーリングを行う
- 近場でもキャンプなどの動画を撮影したい
- タンデムツーリングで恋人との思い出を作りたい
…などなど。こんなシチュエーションが思い浮かびます。もちろん釣りをしに行くとか、そういうことも含まれているのだろうとは思いますが。ということはアクションカメラの設定やアクションカメラの冷却道具に頼るより、実際にバイク自体に冷却道具を積めるよう、リアキャリアなどを改造してクーラーボックスなどを取り付ける方がいいわけです。
リアキャリアの取り付けが行える方なら、後は穴を開けるドリルなどの道具があれば取り付けは簡単に行えます。この際にコンテナの改造なども視野に入れてみてはいかがでしょうか?

まとめ
DJI Osmo Action 3は高画質な映像を実現する一方で、発熱という宿命的な課題を抱えています。特に4K/120fpsなど高負荷設定や真夏の屋外では熱暴走リスクが高まり、撮影が中断されることも。しかし、撮影設定を工夫したり、外部冷却アイテムを活用することでそのリスクを最小限に抑えることは可能です。
重要なのは「用途に応じて設定を最適化すること」と「環境に応じた冷却対策を取ること」です。そして仮に熱暴走が起きても、それは保護機能が働いた証拠であり、即座に故障を意味するわけではありません。適切な対策を組み合わせれば、Osmo Action 3をより安心して長時間使い続けることができます。あなたの大切なワンシーンを記録するために、今日からできる熱対策を取り入れてみてください。
以前はGoProをおススメしていたのですが、私は今ならアクションカメラはInsta360とDJI Osmo Actionを支持しています。私も別にアクションカメラを信奉しているわけではないのですが、あくまで選択肢は多い方がいいという意味で熱暴走の危険を分散するという考えです。
今回はDJI Osmo Action3の記事ですがこの上位モデルのDJI Osmo Action4というアイテムも売っています。Insta360とこちらの製品は非常に熱暴走に強いと評判がいいので、もし私の考えのようにアクションカメラの選択肢を持っておこうと思った方がいたら、上位モデルのDJI Osmo Action4も参考にしてください。

DJI アクションカメラ Osmo Action 4 スタンダードコンボ 4K/120fps対応 防水アクションカメラ 1/1.3インチセンサー搭載 驚きの低照度性能 10-bit & D-Log M カラーパフォーマンス 長時間駆動の1770 mAhバッテリー 【国内正規品】